姫路城の白さは、まるで神々の手によって磨き上げられたかのようだった。改修直後のその姿は、まさしく「白鷺城」の異名にふさわしい。青空に映える純白の天守閣は、静かに悠久の時を語りかけてくるようであり、私はしばし言葉を失った。

歴史の足音と池田輝政の野望
姫路城の歴史を遡ると、その原点は14世紀、赤松貞範が築いた砦にたどり着く。しかし、それは今の壮麗な城とは似ても似つかぬ、単なる防衛拠点だった。戦国時代に入ると、黒田官兵衛(孝高)が織田信長の命により城を整備し、さらに羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が天守を築いた。この時の城は、今よりも規模が小さく、戦国の気配を色濃く残していた。
転機が訪れたのは、関ヶ原の戦いの後だ。1600年、徳川家康の天下統一が決まると、彼は家臣団の領地を再編成し、西国の要所に信頼のおける大名を配置した。池田輝政が姫路城を与えられたのも、この戦略の一環だった。輝政は、徳川政権の西国支配を盤石にするため、姫路城を「軍事的拠点」から「権威の象徴」へと作り変えることを決意する。
その結果、城は日本最大級の規模へと拡張された。五重の大天守を中心に、三重の小天守が連結する優美な構造。白漆喰で塗り固められた壁は、戦国の荒々しさを脱し、まるで天空に舞う白鷺のような姿を見せる。石垣は高く、巧みに曲線を描き、侵入者の足を鈍らせた。さらに、複雑に入り組んだ通路と多数の門は、敵を容易には天守へ近づけさせない仕組みになっていた。この城は、単なる防衛施設ではなく、徳川の威光を示す象徴的な城郭だったのだ。

戦火を超えて、世界の遺産へ
江戸時代を通じて、姫路城はそのままの姿を保ち続けた。戦のない時代が続き、城は平和の象徴となった。明治の廃城令により、多くの城が取り壊される中、姫路城も一度はその運命を辿るかと思われた。しかし、城の歴史的価値を理解する人々の努力によって、存続が決まり、大正・昭和の修復工事を経て現代へと受け継がれた。
1993年、姫路城はユネスコ世界文化遺産に登録される。その際、国際的なプレゼンテーションで強調されたのは、姫路城が「日本の木造城郭建築の最高傑作」であること、そして「戦火を逃れ、江戸時代の姿をほぼ完全に残している唯一の城」であるという点だった。さらに、城郭全体のデザインが「機能美と芸術性を兼ね備えた建築」として評価され、城下町の発展にも大きく寄与したことが文化的意義として挙げられた。
特に、日本独自の「白漆喰総塗籠造り」が、他国の城郭建築には見られない特異な特徴として注目された。この白い城壁は、見た目の美しさだけでなく、防火性・耐久性にも優れた実用的な工夫でもあった。姫路城の登録は、日本が世界に誇る文化遺産の価値を再認識させる出来事となった。
意外なる味覚との遭遇
城を後にし、私はふとした好奇心から地元の食を探してみることにした。観光客向けの店では「姫路おでん」や「播州ラーメン」といった名物が並んでいたが、私が足を止めたのは、ひつまぶしのように供される穴子飯だった。
うなぎではなく、穴子。それは意外でありながら、瀬戸内の海が育んだ確かな味わいだった。姫路の近く、播磨灘では質の高い穴子が獲れる。それを炭火で香ばしく焼き、甘辛いタレを絡めてご飯にのせる。口に運ぶと、ふっくらとした穴子がほろほろとほどける。わさびが爽やかに香り、最後に出汁をかければ、また違った味わいへと変化する。旅人の疲れを優しく癒すその料理は、姫路という土地の奥深さを静かに教えてくれた。

帰路につきながら、私は改めて思った。旅とは、ただ景色を見ることではなく、その土地の空気を吸い、その味覚を楽しみ、そこに流れる歴史を感じることなのだ。姫路城の白さは、時が経つにつれて少しずつ落ち着きを増していくだろう。しかし、その輝きが失われることは決してない。



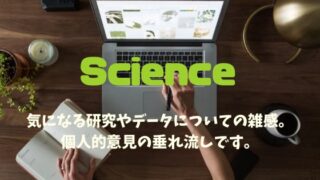
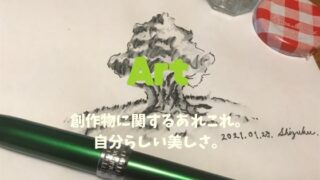



コメント