「頭の回転が速いが、浅い思考になりがち」「じっくり考えるのは得意だが、即断即決が苦手」——このような思考の違いを感じたことはないでしょうか?
私たちの思考には、速く直感的に判断する「回転の速い思考」と、時間をかけて粘り強く考える「トルクのある思考」の2種類が存在するという言説があります。
この2つの思考モードを適切に切り替え、場面に応じて使い分けることができれば、仕事や人間関係、創造的な活動においても、より優れた判断ができるようになります。本記事では、学術的な知見と実生活に考えを巡らせながら、「思考の使い分け」の重要性と、それを鍛える具体的な方法を探っていきます。
速い思考 vs. 深い思考:2つの思考モードとは?
まず、人間の思考プロセスには、大きく分けて2つのモードがあるとされています。
1. 速い思考(回転が速いが馬力が小さい)
• 直感的で素早い判断が可能
• 日常の習慣や経験に基づいて即決する
• 瞬時のリアクションが必要な場面で活躍
• ただし、思考が浅く、間違った結論に飛びつくリスクがある
2. 深い思考(回転が遅いがトルクが大きい)
• 時間をかけてじっくり考える
• 複雑な問題を多角的に分析し、粘り強く取り組む
• 長期的な戦略や根本的な問題解決に向いている
• ただし、決断までに時間がかかり、スピードが求められる場面では不利
この2つの思考モードは、心理学者キース・スタノヴィッチ(Keith Stanovich)とリチャード・ウェスト(Richard West)が1999年に提唱しました。
その後、ノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマンの著書『ファスト&スロー』でも広く紹介されます。カーネマンは、これを「システム1(速い思考)」と「システム2(遅い思考)」と呼び、私たちが日々の意思決定を行う際、この2つのモードを無意識に切り替えていることを示しました。
しかし、単に「直感」と「論理」を鍛えれば良いわけではないと個人的には考えています。重要なのは、場面に応じてこの2つを適切に使い分けられること、そして他者の感情を慮り、多角的な視点を持つことではないでしょうか。
環境が思考スタイルに影響を与えるのではないか、というシズク的仮説
例えばあくまで私の肌感に基づく意見ですが、IT業界においては技術の進歩が非常に速く、エンジニアやプログラマーは常に最新の知識やスキルの習得が求められます。このため、迅速な思考を重視する方が多いように感じます。
これは純粋に興味深いことで、自分が従事する業界や国といった環境が、上で述べた2つの思考モードになんらかの作用を持つのだとしたら、脳の発達や心理的課題の有無などを考察する意義は大きいのではないでしょうか。
少なくとも技術の本質的な理解や革新的なアイデアの創出には、深い思考も不可欠です。このように環境によって2つの思考モードに何らかの影響を与えうるのか、またそうだとしたら注意すべき点はあるのかといった研究も面白いかもしれません。
2つの思考モードをどう鍛えるべきか?
思考力を鍛えるというと、「速く論理的に考える訓練」と「感情をコントロールする訓練」が思い浮かびます。しかしながら私個人の意見としては、それだけでは十分ではないと考えています。
「深い思考」を鍛えるためには、関わる人それぞれの感情を慮り、多角的な視点を持つことが重要です。自分だけの視点にとどまらず、相手の価値観や社会的背景を理解しながら考えることで、より粘り強い思考が可能になると感じています。
では、どのように2つの思考モードを鍛えていけばよいのでしょうか?ここからはそれぞれの思考モードの訓練方法について、個人的な(独断と偏見による)提案をしてみようと思います。
速い思考を鍛える方法
• タイムプレッシャーをかけた決断を練習する(例:即興スピーチ、短時間での問題解決)
• ゲームやクイズで瞬発的な判断力を磨く(例:囲碁・将棋、戦略ゲーム)
• 「最初の直感」を意識し、それが正しいか検証する習慣を持つ(直感を磨きつつ、検証力も養う)
深い思考を鍛える方法
• 異なる立場から物事を考える(例:「自分がこの人だったらどう考えるか?」と想像する)
• 議論を通じて、多角的な視点を得る(例:読書会に参加する)
• 「Why?(なぜ?)」を繰り返して思考を深める(例:ある問題について「なぜそうなったのか?」を自問自答してみる)
• 一人で考える時間を意図的に作る(例:散歩しながら思考を整理する、日記を書く)
速い思考と深い思考をバランスよく使うための習慣
実際の生活や仕事では、「速い思考」と「深い思考」を適切に切り替えることが求められます。バランスの取れた思考を取り入れるための入り口について、周囲の人々を参考に考えてみました。
1. 「決断の速さ」と「考える時間」のメリハリをつける
日常の些細な選択(食事や服装など)は速く決め、大事な決断(キャリアや人生の選択)は時間をかけて考える。
2. 短期的な課題と長期的な目標を意識的に分ける
「この問題は今すぐ解決すべきか?」「時間をかけてじっくり取り組むべきか?」と判断する癖をつける。
3. 自分の意見に対する「反対意見」を考える
「自分と異なる意見の人はどう考えるか?」を想像し、思考の偏りを防ぐ。
4. 「心の余裕」を持つことで、深く考える時間を確保する
ストレスが多いと、どうしても「速い思考」に偏りがちになるため、意識的にリラックスする時間を作る。
まとめ
速い思考(システム1)と深い思考(システム2)は、それぞれにメリットとデメリットがあります。重要なのは、これらをバランスよく使いこなし、場面に応じて適切に切り替えることです。
また、単なる「速さ」と「論理性」だけでなく、他者の感情を理解し、多角的な視点から物事を見ることが、深い思考を鍛えるカギとなります。
例えば岡田斗司夫氏は、さまざまなジャンルの知識を融合させ、新しい視点を提供することで、時代を超えて影響を与え続けていますが、やはり頭の回転と思考力について、独自の見解を示されています。速い思考と深い思考を自在に使いこなし、知的な柔軟性を持つことが、これからの時代に求められるスキルなのかもしれません。
あなたは、どんな場面で「速い思考」と「深い思考」を使い分けていますか? オススメの訓練法があれば、ぜひコメントでご教示ください!



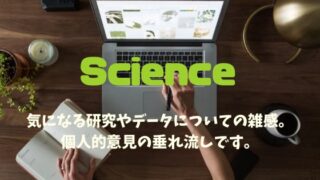
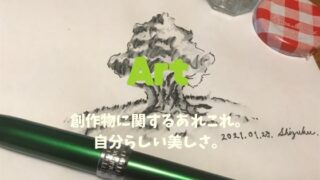




コメント