輸血ができない状況を救う、新たな技術とは?
輸血は医療現場で欠かせない治療法ですが、血液型の違い、感染リスク、保存期間の限界など、さまざまな課題があります。特に、大規模災害や救急医療、離島・僻地での治療では、輸血の確保が難しい場面が多々あります。
そこで、日本の研究チームが開発を進めているのが、人工赤血球(ヘモグロビンベシクル、HbV)です。これは、赤血球の代わりに酸素を運ぶことができる人工血液製剤で、長期保存が可能で、血液型の違いを気にせず使える という特徴を持っています。
この研究は、奈良県立医科大学、旭川医科大学、北海道大学が協力して行っており、2022年8月にその臨床試験(第一相試験)の結果が発表されました。
人工赤血球(HbV)とは?
人工赤血球(HbV)は、直径約250nmの小さなリポソームに、ヘモグロビン(酸素を運ぶタンパク質)を閉じ込めたものです。通常の赤血球と同じように、肺で酸素を取り込み、全身に運ぶことができます。
主な特徴
・血液型を気にせず使える → どんな患者にも投与可能
・感染症リスクが低い → ヘモグロビンを精製・処理することで安全性を確保
・長期保存が可能 → 既存の血液よりも長く保存できるため、災害時や救急医療に役立つ
原料となるヘモグロビンは、廃棄予定の献血血液から精製して作られているため、医療資源の有効活用にもつながります。
今回の臨床試験(第一相試験)では、健康な成人男性に異なる量のHbVを投与し、安全性や体内での動きを確認しました。
その結果、HbVがヒトに安全に投与できる可能性が示されました。現在は、さらに多くの量を投与する第二相試験の準備 が進められています。
他の人工血液研究との違いは?
人工血液の研究は、日本だけでなく、アメリカやヨーロッパでも行われています。例えば、アメリカではバイオテクノロジー企業が「人工ヘモグロビン」を開発 し、軍事医療や災害時医療への応用を目指しています。
しかし、HbVには「血液型フリー」「長期保存可能」「感染リスクが低い」という強みがあります。他の人工血液と比べても、実用化の可能性が高い技術として注目されています。
今後の展望:実用化に向けた次のステップ
今回の臨床試験で安全性が確認されたことで、HbVの実用化に向けた大きな一歩が踏み出されました。今後は、さらに多くの人を対象にした試験(第二相試験)を行い、安全性と効果を確認する必要があります。
もし実用化されれば、輸血が難しい環境でも酸素供給が可能となり、医療の幅が大きく広がることが期待 されています。特に、救急医療や災害医療の現場では、大きな革命となるでしょう。
引き続き、HbVの開発動向に注目していきましょう!



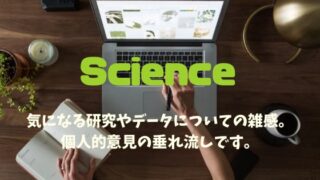
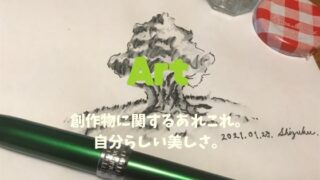



コメント